「月々の返済、本当にこれで大丈夫…?」その不安、正解です

「住宅ローン控除があるから今が買い時!」
不動産会社でそう言われて、なんとなく「そうなのかな…」と物件探しを始めたあなた。
でも心の中では、「本当に35年も払い続けられるの?」「子どもの教育費、足りるかな…」という不安がモヤモヤしていませんか?
その直感、実は大正解なんです。
私は不動産仲介エージェントとして、これまで多くのご家族の住宅購入をサポートしてきました。その中で気づいたのは、住宅ローン控除だけを見て判断すると、将来「こんなはずじゃなかった」と後悔する方が本当に多いということ。
たった10分で、これからの35年間の安心が手に入ると思って、最後まで読んでみてください。


この記事を書いた人:🏠 むちのち TERASSパートナー/子育てパパ×不動産エージェント
「いい不動産取引は、いいエージェントから。」
私はこの理念を胸に、ノルマのない環境で活動しています。(TERASSについてはこちら)
だからこそ実現できるのが、徹底した「売らない営業」。 お客様のペースを大切にし、本当に価値ある物件だけをご紹介します。将来の資産性も含め、プロとして厳しい目線でチェックします🔍
- ✅ 全国の物件紹介やエリア調査も【完全無料】
- ✅ 「相談=契約」ではありません。セカンドオピニオンも歓迎
- ✅ 家族全員が満足できる“賢い選択”を一緒に見つけます👨👩👧👦
まずはこの記事でノウハウを収集👇
気になる物件のURLを送るだけの「簡易診断」もLINEで人気です!いつでもLINEへどうぞ!
まず知っておきたい!住宅ローン控除の「本当の価値」
そもそも住宅ローン控除って、どれくらいお得なの?
2025年現在、住宅ローン控除は年末のローン残高の0.7%が最大13年間(新築の場合)、税金から戻ってくる制度です。
でも、ちょっと待ってください。
「最大で」という言葉、気になりませんか?
実は多くの方が勘違いしているのですが、控除額がそのまま全額戻ってくるわけではありません。
【重要】実際に戻ってくる金額の考え方
| 項目 | 説明 |
|---|---|
| 控除の仕組み | 年末ローン残高×0.7%(※2025年現在) |
| 控除期間 | 新築:最大13年間、中古:10年間 |
| 上限の考え方 | 納めている所得税・住民税の範囲内 |
| 住宅の種類による違い | 省エネ性能が高いほど借入限度額が優遇 |
※2025年度税制改正により、子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置が延長されています
先日ご相談いただいた会社員のAさんも、「控除があるから大きく借りても大丈夫」と思っていたのに、実際の還付額が想定よりかなり少ないことがわかって愕然としていました。



住宅ローンって難しくてわからない…
金利、団信、返済比率、住宅ローン控除…どれも聞き馴染みなくて確かに難しいですよね…。
でも大丈夫。
そんなあなたのために『住宅ローンのまとめ記事』を作成しています!
色々調べたことがある方も、そうでない方もみなさんに知ってほしい情報をギュッと集めました。


【要注意】こんな人は資金計画を見直すべき5つのサイン
1. 「控除が終わる14年目」を想像できていない人
💡 あなたは大丈夫?チェックリスト
□ 14年後の自分の年齢を即答できない
□ その時の子どもの学年がわからない
□ 控除終了後の月々の返済額を計算していない
控除期間が終わると、実質的な負担が増えることを忘れてはいけません。
実際にあった話をご紹介しますね。
38歳で家を購入されたBさんご夫婦。当初は控除のおかげで実質負担は想定内でした。
ところが、控除が終わると同時に長男が大学進学、次男が高校進学。教育費が急増し、住宅ローンと合わせて家計が急激に圧迫される状況に…。
2. 教育費を「なんとかなる」で済ませている人
教育費は子どもの成長とともに変化します。特に注意が必要なのは高校・大学の時期です。
| 時期 | 教育費の傾向 | 住宅ローンとの関係 |
|---|---|---|
| 幼児期 | 比較的抑えめ | 返済初期と重なる |
| 小学生 | 安定期 | 控除期間中 |
| 中高生 | 徐々に増加 | 控除終了時期と重なる可能性 |
| 大学生 | ピーク期 | 返済中盤〜後半と重なる |
文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、幼稚園から高校まですべて公立でも相当な費用がかかり、大学まで含めると更に負担は増加します。
住みやすさやローンの悩みはもちろん、 「ネットで毎日探してるけど、いい情報がない…」とお困りの方もLINEへどうぞ💬
🔍 ポータルサイトで見つからない理由、知っていますか??



実は、売主様の事情や広告のタイミングで「ネットには載らない物件」がたくさんあります。
私なら、業者専用システムの情報網を使って、お客様がまだ知らない「ポータル非掲載の物件」まで幅広くご紹介可能です。
- ✅ あなたに代わって、隠れた優良物件を探します
- ✅ 気になったことは、チャットで気軽に質問OK
選択肢を広げるために、まずは情報を受け取れる状態にしておきませんか?
3. 「共働きだから余裕」と考えている人
💡 収入減少リスク診断
□ 2人目、3人目の出産予定がある
□ 実家が遠方で、親の介護が心配
□ どちらかが転職を考えている
□ 時短勤務の可能性がある
1つでも当てはまったら、世帯収入が減少する可能性を考慮した計画が必要です。
実例をお話しします。
共働きのご夫婦が、2人の収入を前提に住宅を購入。ところが、2人目の出産を機に働き方を変更せざるを得なくなり、世帯収入が大きく減少。貯金を切り崩す生活に…。
「まさか自分が仕事を辞めるなんて思ってもいなかった」と奥様。
厚生労働省の「令和4年版働く女性の実情」によると、第1子出産を機に離職する女性は依然として一定数存在します。
4. 車の買い替えを「その時考える」人
車を所有している場合、維持費は想像以上にかかります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 車両代 | 定期的な買い替えが必要 |
| 維持費 | 税金、保険、車検、メンテナンス |
| 燃料費 | ガソリン代、電気代(EV車) |
| 駐車場代 | 地域により大きく異なる |
月換算すると、2台所有の場合は住宅ローンとは別に相当な固定費がかかります。
「車なんて乗れればいい」と思っていても、子どもが大きくなれば「もう少し広い車が…」となるもの。計画的に準備しないと、カーローンで更に家計が圧迫されます。



私も1歳と0歳の子供がいますが、チャイルドシートのことや毎日の生活、先々のことを考えて大きい車を購入しました🧐
5. 「老後はまだ先」と思っている人
💡 老後資金準備の重要性
- 65歳時点で住宅ローンが残っている人は一定数存在
- 老後資金の準備は早く始めるほど有利
- 複利効果を活用できる期間が長い
金融庁の「高齢社会における資産形成・管理」報告書でも、老後の生活設計の重要性が指摘されています。
プロが実践する「失敗しない資金計画」3ステップ
ステップ1:まずは「本当の手取り額」を知る
多くの方が年収ベースで計算しますが、大切なのは手取り額です。
📊 簡単計算フォーマット
月収総額から税金・社会保険を引いた手取り月収を把握 その25%以内が安心して払える住宅ローンの目安
この25%ルールを守れば、急な出費があっても対応できます。
ステップ2:「見えない出費」を見える化する
年間の特別支出をリストアップしてみましょう。
📝 年間特別支出チェックリスト
- □ 固定資産税
- □ 火災保険・地震保険
- □ 家電買い替え費用
- □ 帰省・冠婚葬祭費
- □ 旅行・レジャー費
これらを月割りすると、意外と大きな金額になります
これらを考慮せずに住宅ローンを組むと、ボーナスがすべて消えていきます。
ステップ3:3つのシナリオでシミュレーション
私がお客様にお勧めしているのは、「楽観・標準・悲観」の3パターンでシミュレーションすること。
| シナリオ | 想定内容 | 返済計画の考え方 |
|---|---|---|
| 楽観シナリオ | 昇給・共働き継続・金利現状維持 | 余裕のある返済 |
| 標準シナリオ | 現状維持・金利若干上昇 | 無理のない返済 |
| 悲観シナリオ | 収入減・金利上昇 | 最低限の返済可能額 |
悲観シナリオでも返済可能な金額が、本当の「身の丈」です。
🏠「家を買う前に、これだけはやっておきたかった…」
実は、マイホーム購入で後悔する人の多くが将来の収支計画を見直すための「ライフプラン」を立てずに決めてしまった」ことが原因です💦
- ちゃんと見直す機会がなかなかないまま…。
- 家を買った後にその場でなんとかやりくり…。
など、ちゃんとした『安心』も買うということを蔑ろにしがち。



そんな状況になってからでは取り返しがつかないことも…。
そこで今、LINE登録いただいた方限定で
- 🔹 ライフプランシート
- 🔹 無料で優秀なFPさんをご紹介
のW特典をご用意しました🎁
お金の見通しを立ててから、安心して家探しをしませんか?
LINE登録後の回答フォームに入力し、キーワードを入力すると受け取り完了!
- ライフプランシートの受け取りを希望の方🎁→『ライフプランシート』で送信
- ライフプラン面談を受けたい方👀→『ライフプラン希望』で送信
よくあるご質問にお答えします
Q1:「フルローンの方が控除でお得」って本当?
A:必ずしもそうとは限りません。総支払額で比較することが重要です。
確かに借入額が多いほど控除額は増えますが、同時に支払利息も増加します。また、頭金を入れることで金利優遇を受けられる場合もあります。個別にシミュレーションして判断しましょう。
Q2:変動金利と固定金利、どっちを選ぶべき?
A:あなたの性格と家計の余裕度で決めましょう。
💭 性格診断チャート
変動金利が向いている人: ✓ 金利動向をチェックできる ✓ 繰り上げ返済の余力がある ✓ リスクを取れる余裕がある
固定金利が向いている人: ✓ 安定を重視したい ✓ 金利上昇が心配 ✓ 家計に余裕が少ない
バランスの取れた「10年固定」などの固定期間選択型を選んぶ方もいます。
Q3:今買うべき?それとも待つべき?
A:「完璧なタイミング」は存在しません。大切なのは「準備ができているか」です。
✅ 購入準備度チェック
- □ 頭金として物件価格の1割以上ある
- □ 別途、生活費6ヶ月分の預金がある
- □ 今後5年間の収入見通しが立っている
- □ 家族の将来像が明確になっている
- □ 複数の物件を比較検討した
4つ以上✓なら、購入を検討する準備ができています!
📩 「お金」のことから「物件」のことまで。 あなたの家探しをトータルで支えます。



「まだ探し始めたばかりで…」
「不動産会社ってなんだか緊張する…💦」
そんな方にこそ、LINEでの“ゆる相談”がおすすめです😊
私の強みは、最初から最後まで一貫してサポートできること。
- ✅ ライフプラン・資金計画(無理のない予算は?)
- ✅ 住宅ローンの事前審査(いくら借りられる?)
- ✅ 物件選定・物件調査(この家は本当に安全?)
面倒な手続きや不安な調査も、すべて私が担当します💪
ちょっとした疑問でも全然OK!無理な営業は一切ありません✋
【注意事項】住宅ローン控除制度について
2025年現在の制度内容
2025年度税制改正により、住宅ローン控除制度は以下のようになっています:
■ 基本的な仕組み
- 控除率:年末ローン残高の0.7%
- 控除期間:新築住宅13年間、中古住宅10年間
- 適用期限:2025年12月31日までの入居
- 所得制限:合計所得金額2,000万円以下
■ 住宅の種類による借入限度額の違い(2025年入居の場合)
| 住宅の種類 | 一般世帯 | 子育て世帯・若者夫婦世帯※ | 最大控除額(13年間) |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | 409.5万円 / 455万円 |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | 318.5万円 / 409.5万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | 273万円 / 364万円 |
| その他の住宅 | 原則対象外** | 原則対象外** | - |
※19歳未満の子を有する世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の世帯 **2023年12月31日までに建築確認を受けた住宅等は借入限度額2,000万円、控除期間10年(最大控除額140万円) ※最大控除額は借入限度額×0.7%×控除期間で計算した理論上の最大値です。実際の控除額は納税額により変動します
■ 重要な変更点
- 2024年以降、省エネ基準を満たさない新築住宅は原則として控除対象外
- 子育て世帯・若者夫婦世帯への優遇措置が2025年も継続
- 床面積40㎡以上50㎡未満の緩和措置も2025年12月31日まで延長(合計所得1,000万円以下の年に限る)
ご注意いただきたいこと
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の物件や状況に対する具体的なアドバイスではありません。
- 物件価格は立地、築年数、設備など多くの要因により大きく異なります
- 購入可能額は個人の収入、支出、ライフプランにより個人差があります
- 税制は毎年改正される可能性があります
- 実際の控除額は個人の納税額により変動します
住宅購入を検討される際は、必ず最新の制度内容を確認し、ファイナンシャルプランナーや税理士などの専門家にご相談することをお勧めします。
【まとめ】本当に大切なのは「家族の笑顔が続く」資金計画
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
もしかしたら、「思ったより厳しい現実だな…」と感じたかもしれません。
でも、事前に知っておけば対策は必ずできます。
私がサポートしたお客様の中には、この記事の内容を実践して、当初検討していた物件から見直し、結果として「ちょうどいい暮らし」を実現された方がたくさんいます。
📌 この記事の重要ポイント
- 住宅ローン控除に頼りすぎない
- 手取り収入の25%以内で借りる
- 教育費・車・老後資金まで含めて計画する
- 悲観シナリオでも返済可能な金額を選ぶ
もし、こんな未来が手に入るとしたら…
ここまで読んでいただいて、きっと今、こんな気持ちではないでしょうか。



「住宅ローン控除のことはわかったけど、結局うちの場合はどうなの?」
「理想的な話はわかるけど、現実的に私たちに当てはめると…?」
そうですよね。一般論はわかっても、自分たちの具体的なケースがわからないと、不安は消えません。
もしこんな状態になれたら、どうでしょう?
✨ 1週間後には…
- 自分たちの「本当の予算」が明確になっている
- 住宅購入の正しい手順がすべてわかっている
- 何から準備すればいいか、迷いがなくなっている
✨ 2週間後には…
- プロのライフプランナーと一緒に、35年先まで見通した資金計画ができている
- 教育費のピーク時でも余裕を持てる返済プランが完成している
- 「この計画なら大丈夫」という確信が持てている
✨ 1ヶ月後には…
- 物件選びの基準が明確になり、迷いなく内覧できている
- 不動産会社の営業トークに惑わされなくなっている
- 家族みんなが納得できる選択ができている
理想的すぎる?
いいえ、これは私がサポートしたお客様が実際に経験された変化です。
でも、こんな不安もありますよね…
😟 「本当に無料で相談なんてできるの?」
😟 「結局、営業されるんじゃないの?」
😟 「ライフプランナーって高そう…」
😟 「忙しくて時間が取れないし…」
その気持ち、本当によくわかります。
だからこそ、まずは気軽に始められる方法を用意しました。
あなたの不安を解消する3つのステップ
- ステップ1:購入準備の正しい知識を身につける 毎日1通、7日間で住宅購入の基礎がすべてわかる資料をお送りします。通勤時間にスマホで読むだけでOK。
- ステップ2:プロのライフプランナーに無料相談 私が信頼する、住宅購入に詳しいFPをご紹介。もちろん相談料は無料です。
- ステップ3:あなたの疑問に直接お答えする オンライン面談で、記事では書けない本音のアドバイスをお伝えします。
もし何もしなかったら…
このまま記事を閉じて、また明日も同じように悩み続ける…
そんな日々が続いたら、1年後も同じ場所にいるかもしれません。
その間に、住宅ローン控除の制度が改悪されたら?
金利が上昇してしまったら?
理想の物件が他の人に買われてしまったら?
「あの時、行動しておけばよかった…」
そんな後悔だけは、してほしくないんです。
今、一歩踏み出すだけで変わること
実は、住宅購入で成功する人と失敗する人の違いは、たった一つ。
「正しい情報を、正しいタイミングで手に入れたかどうか」
それだけなんです。
今なら、その第一歩を無料で踏み出せます。
✅ 条件をクリアして「TERASS Picks※」と連携!
【思考の整理 × 物件情報 = 失敗しない家探し】
あなたの条件に合う「物件情報」をSUUMOなどのポータルサイトと、不動産業者しか見れない情報サイト『REINS』から自動で収集しつつ、 状況に合わせて「あなたに最適な進め方」を選んでいただけます。
🔰 LINE登録でできること(選べます!)
📚 じっくりコース(準備期間:半年以上の方)
- 「失敗しないための7日間準備プログラム(資料)」で知識をつける。
- その後は自分のペースで進めてOK!
無理に急かすことはありません。面談も物件情報も、必要だと思う時にお声がけくださいね☺️
🚀 最短コース(準備期間:今すぐ〜半年未満の方)
- ネットに出ない「未公開情報」の紹介や、資金計画の相談を最優先で対応します🏠
- 一般の方は見られない業者専用データベース(レインズ)から、あなたの条件に合う「水面下の優良物件」をこっそり共有します。
⚠️ 正直にお伝えします
私は物件だけでなく「周辺環境」や「騒音」まで徹底的に調査するため、 ご案内できる方に限りがございます。 (※定員を超えた場合は、信頼できるTERASS エージェントの紹介、または翌月のご案内となります)
『失敗しない家探し』をご希望される方は、ぜひお早めにご相談ください!
📗定期配信もあります!(準備期間:全ての方対象)
- 不動産に関わる大事なニュース(住宅ローンの金利動向、市場動向、法改正などなど…)をプロの解説を交えて不定期で配信!
- 馴染みのない方でもわかりやすく!を大事にしています👌
👇 あなたはどっち派?まずは登録して選択!(30秒で登録)
※しつこい営業は一切ありません。ブロックも自由です。
※「TERASS Picks」は、株式会社TERASSの登録商標またはサービス名です。
※しつこい営業は一切しません
※いつでもブロック可能です
最後に…
「でも、やっぱり迷う…」
その気持ち、本当によくわかります。
でも、LINEの友だち追加は30秒でできます。
もし合わないと思ったら、すぐにブロックすればいいだけ。
失うものは何もありません。
でも、得られるものは…
これからの35年間の、家族の安心と幸せです。
今この瞬間が、あなたの人生を変える第一歩になるかもしれません。
追伸:「もっと早く相談すればよかった」これが、私のお客様から一番多く聞く言葉です。あなたには同じ後悔をしてほしくありません。今すぐ、最初の一歩を踏み出してください。
【参考情報】
本記事の作成にあたり、以下の公的機関・信頼できる情報源を参照しました:
■ 住宅ローン控除制度について
- 国土交通省「住宅ローン減税」 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
- 国税庁「住宅借入金等特別控除」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
■ 税制改正について
- 財務省「令和7年度税制改正の大綱」 https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/index.html
■ 教育費について
- 文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」 https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/mext_00001.html
■ 老後資金について
- 金融庁「高齢社会における資産形成・管理」 https://www.fsa.go.jp/singi/singi_kinyu/tosin/20190603.html
■ 働く女性の実情について
- 厚生労働省「令和4年版働く女性の実情」 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/josei-jitsujo/22.html
※本記事の内容は2025年8月13日時点の情報に基づいています。 ※税制や各種制度は変更される可能性があります。最新情報は各公的機関のウェブサイトでご確認ください。








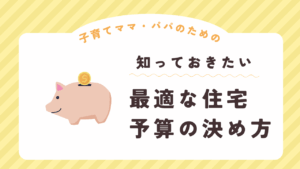

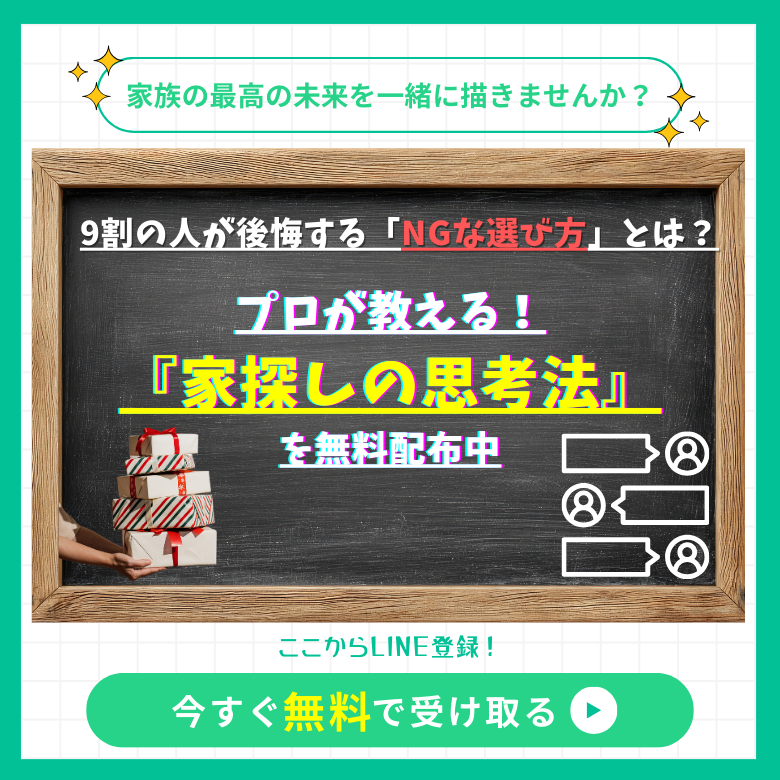
コメント